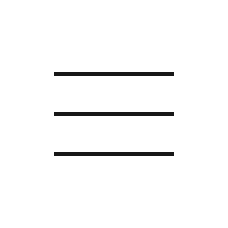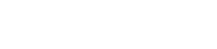- 疲れやすい・疲れが取れない‥
慢性疲労でお悩みの方へ - 疲れやすい・疲れが取れない時に
考えられる疾患 - 慢性的な疲労感が続く原因とは?
- 慢性疲労の検査方法
- 慢性疲労の治療方法
- 疲れにくい体をつくる5つの習慣
- 疲れやすさ・取れない疲れには、
根本へのアプローチを
疲れやすい・疲れが取れない‥
慢性疲労でお悩みの方へ
「なんだかだるいな」「疲れが残っていて仕事に身が入らない」
多くの方が、一度はご経験があるかと思います。ひと晩しっかり眠ったり、気分をリフレッシュしてすぐに元気になれれば問題ありませんが、症状が続く場合には、当院までご相談ください。

- なんとなくだるい感じが続いている
- 休んだのに疲れが抜けない感じがする
- 疲労感、倦怠感から、ヤル気が出ない
- 食欲が出ない
- 集中力や思考力の低下、ケアレスミスの増加
- 気分が落ち込み、好きなことを楽しめない
- 夜中に何度も目が覚める
- 休日、お昼頃まで寝てしまう
- 頭痛、肩こりなどの不定愁訴が続いている
疲れやすい・疲れが取れない時
に考えられる疾患
疲労感や倦怠感を症状に持つ主な疾患をご紹介します。
糖尿病
膵臓から分泌されるインスリンの働きや分泌量が低下することで、慢性的な高血糖になる病気です。初期はほぼ無症状ですが、進行すると疲労感・倦怠感、のどの渇き、頻尿、体重減少などの症状が現れます。
慢性疲労症候群
日常生活に支障をきたすほどの疲労感が6ヶ月以上続いている状態です。「十分な休息をとっても回復しない」という点が診断のポイントになります。はっきりとした原因は分かっていません。
甲状腺機能低下症(橋本病)
甲状腺ホルモンの分泌が少なくなり、全身の新陳代謝が低下する病気です。疲労感、無気力、食欲不振、体重増加、寒気、むくみ、便秘、動作緩慢、月経不順、抑うつといった症状が見られます。
睡眠時無呼吸症候群
肥満や顎の小ささなどを原因として気道が狭くなり、睡眠中に繰り返し無呼吸・低呼吸を繰り返す病気です。日中、強い眠気に加え、疲労感・倦怠感、集中力の低下、頭痛などの症状が見られます。
うつ病
強いストレスを主な原因として、著しく気分が落ち込む病気です。疲労感、不眠・過眠、興味・関心の低下、食欲不振などの症状を引き起こします。
慢性的な疲労感が続く
原因とは?
病気がなくても、疲労感が続く場合があります。ほとんどは生活習慣が原因となっているため、その習慣を見直せば、症状も改善することが期待できます。
睡眠不足
 睡眠時間が不足していたり、睡眠の質が低下すると、十分に心身を休められず、疲労を翌日に持ち越してしまいます。
睡眠時間が不足していたり、睡眠の質が低下すると、十分に心身を休められず、疲労を翌日に持ち越してしまいます。
「眠りたいけれど眠れない」という場合には、以下のような工夫をしてみてください。
| 起床時間 | 休日を含め、起床時間はできるだけ一定にしましょう。午前中に日光を浴びれば、体内時計が整い、毎日同じ時間帯に眠気が訪れやすくなります。 |
|---|---|
| 日中の活動 | 仕事、遊び、趣味、運動など何でも構いませんが、日中はある程度活発に動きましょう。適度な疲労感が、睡眠の質を高めてくれます。 |
| 食事の時間 | 食事の時間を一定にすることは、生活リズムを整えるのに一役買います。また、夜遅くの食事は控えましょう。 |
| お風呂 | 血流を改善し、心身をリラックスさせるため、お風呂はシャワーだけで済ませずお湯に浸かることをおすすめします。 |
| カフェイン・アルコール | 夕方以降は、カフェインを控えましょう。お酒は夕食の時に飲むという人が多いでしょうが、避けるのが理想的です。少なくとも寝酒はやめましょう。 |
| パソコン・スマホ | 頭・目を休ませるため、夜間のパソコン・スマホの使用は必要最低限にしましょう。特に、ベッドにスマホを持ち込むのはおすすめしません。 |
運動不足
運動は、代謝のアップ、血流の改善、疲労物質の排出促進など、さまざまな効果が期待できます。また、筋力の維持・強化、心のリラックスという点からも、適度な運動習慣を身につけることをおすすめします。
疲れ切るような運動、嫌いな運動をする必要はありません。ウォーキング程度の軽い、ご自身の好きな運動を継続的に行いましょう。
食生活の乱れ
タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂りましょう。自炊ができれば理想的ですが、近年は栄養バランスにこだわった飲食店、お弁当を出すお店も増えています。うまく利用しましょう。
一方で避けたいのが、食べ過ぎ・早食い・就寝前の食事・糖質の摂り過ぎです。
ストレス
ストレスは、生活リズムの乱れ、睡眠不足などと同様に、自律神経のバランスを崩し、疲労感や倦怠感の原因となります。ストレスを溜め過ぎないこと、うまく解消することが大切です。
慢性疲労の検査方法
 慢性的な疲労感には、睡眠不足や栄養の偏り、ホルモンバランスの乱れ、腸内環境の悪化など、さまざまな要因が複雑に関与していることがあります。原因が一つに特定しづらく、一般的な検査では異常が見つからないことも少なくありません。 当院では、「なぜ疲れが取れないのか」「体の中で何が起きているのか」を明らかにするために、多角的な検査を行い、根本的な原因にアプローチしていきます。
慢性的な疲労感には、睡眠不足や栄養の偏り、ホルモンバランスの乱れ、腸内環境の悪化など、さまざまな要因が複雑に関与していることがあります。原因が一つに特定しづらく、一般的な検査では異常が見つからないことも少なくありません。 当院では、「なぜ疲れが取れないのか」「体の中で何が起きているのか」を明らかにするために、多角的な検査を行い、根本的な原因にアプローチしていきます。
血液検査(栄養解析)
一般的な項目に加え、体内の炎症、副腎疲労、各種酵素の活性度、ビタミン・ミネラルバランスといった項目について、分子栄養学的な視点から評価します。「栄養が足りているか」、そして「正しく使われているか」が分かります。
唾液コルチゾール検査
1日6回採取した唾液から、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌リズムを分析します。また、副腎の疲弊度を把握する上で重要になるホルモン(DHEA)も測定し、慢性的に身体が受けるストレスにどのように対応しているかを調べます。
有機酸検査
尿中に排泄される代謝産物(有機酸)を調べ、腸内環境や栄養素の代謝効率、ミトコンドリア機能(エネルギー産生)、神経伝達物質の代謝、解毒機能などを多角的に評価します。栄養アプローチ、生活改善指導に役立ちます。
GI-MAP®検査
最先端のDNA解析を用いた便検査です。腸内の善玉菌・悪玉菌のバランス、ピロリ菌・カンジダ菌・寄生虫・カビの有無、腸の炎症の状態、消化酵素の分泌、免疫機能などについて調べます。免疫やアレルギー、自律神経系の不調に対する精査として有用です。
エピクロックテスト
血液中のDNAのメチル化パターンを分析して、「生物学的年齢」を評価する検査です。加齢に伴う遺伝子発現の変化、修復力の低下などを把握できるため、エイジングケアの指針となります。健康長寿を目指したい方、早期老化のリスク管理をしたい方におすすめです。
慢性疲労の治療方法
幹細胞治療
患者様の腹部から採取した脂肪細胞から幹細胞を取り出し、培養・精製した上で点滴投与する再生医療の1つです。幹細胞が有する組織の修復・再生能力、抗炎症作用により、疲労回復の効果が期待できます。
幹細胞培養上清液
幹細胞の培養の過程で分泌される、成長因子やサイトカイン、エクソソームなどを含む上澄み液を、点滴や局所注射、点鼻で投与する再生医療の1つです。疲労回復、エイジングケア、免疫調整、自律神経のバランスの正常化といった効果が期待できます。
NAD⁺注射
体内でのエネルギー産生に欠かせない補酵素(NAD⁺)を、注射で投与します。慢性疲労の改善、集中力・記憶力アップ、睡眠の質の改善、美肌効果・エイジングケア、代謝の促進などが期待できます。
プラセンタ注射
ヒトの胎盤由来のプラセンタ製剤を注射投与します。成長因子・アミノ酸・ビタミンの作用により、疲労・体力の回復、慢性腰痛・肩こりの改善、新陳代謝の活性化、血行促進、自律神経の調整、更年期障害の改善などの効果が期待できます。
各種点滴(肝臓デトックス、バイオリジェンスペシャル点滴、マイヤーズカクテル点滴など)
エネルギー代謝を改善し疲労を軽減する肝臓デトックス点滴、ビタミンB群・高濃度ビタミンC・グルタチオン・マグネシウム・カルシウムなどを高濃度で配合したバイオリジェンスペシャル点滴、慢性症状改善・自律神経の調整・免疫力アップが期待できるマイヤーズカクテル点滴などをご用意しております。
ナチュラルホルモン補充療法
ナチュラルホルモン(体内のホルモンと分子構造が同一のホルモン)を補充する治療です。血液検査や唾液検査からホルモン評価を行った上で、患者様お一人おひとりに合った、バランスの良い補充を行います。
サプリメント補充
慢性的な疲労や体調不良の背景には、ビタミン・ミネラル・アミノ酸などの栄養素不足が関係していることも少なくありません。サプリメント補充は、不足しがちな栄養素を適切に補うことで、エネルギー代謝の改善や細胞の修復、免疫力の維持をサポートする治療です。
疲れにくい体をつくる5つの習慣
十分な睡眠の確保
慢性的な疲労や体調不良の背景には、ビタミン・ミネラル・アミノ酸などの栄養素不足が関係していることも少なくありません。サプリメント補充は、不足しがちな栄養素を適切に補うことで、エネルギー代謝の改善や細胞の修復、免疫力の維持をサポートする治療です。
食習慣の改善
三大栄養素、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂りましょう。糖質と一緒にビタミンB1を摂ると、エネルギーに変換されやすく、疲労回復に役立ちます。食べ過ぎ・早食い、お酒の飲み過ぎなどは控えましょう。
適度な運動
適度な運動は血行を促進し、乳酸の排出を促します。また、セロトニンが分泌されることで、自律神経が整います。筋力や体力を維持・向上という意味でも、運動習慣は大切です。特にデスクワークをする人は運動不足になりがちなので、意識しましょう。
お風呂では湯船に浸かる
湯船に浸かると、血液・リンパ液の流れが良くなり、老廃物の排出が促されます。また、筋肉の緊張が和らぐこと、心もリラックスすることから、疲労回復に適しています。お湯が熱すぎると逆に疲れてしまうため、ややぬるめのお湯に浸かりましょう。
ストレッチ
ストレッチは、血行改善、筋肉のリラックス、全身への酸素供給の促進、乳酸の排出促進など、疲労回復につながるさまざまな効果が期待できます。入浴後や就寝前などに、ストレッチをしてみてください。
疲れやすさ・取れない疲れ
には、根本へのアプローチを
 「年齢のせい」「体質のせい」と、慢性的な疲れをあきらめていませんか?
「年齢のせい」「体質のせい」と、慢性的な疲れをあきらめていませんか?
原因がわからないまま放置されがちな慢性疲労は、日常生活の質を大きく低下させるだけでなく、体の内側で進行するさまざまな不調のサインであることも少なくありません。
当院では、一時的に元気を取り戻す対症療法ではなく、「なぜ疲れが取れないのか」「どこに不調の原因があるのか」を見極める根本的なアプローチを大切にしています。
血液検査や栄養解析、有機酸検査、ホルモンバランスの評価などを通して、ミトコンドリア機能の低下、慢性炎症、腸内環境の乱れ、栄養素の欠乏、ホルモンのアンバランスといった疲労の背景を丁寧にくみ取り、必要に応じて再生医療や点滴療法、ホルモン補充療法などの個別ケアをご提案いたします。
「なんとなく疲れている」を放置せず、ぜひご相談ください。