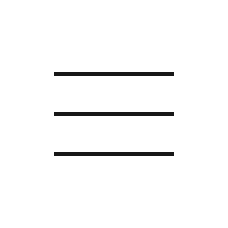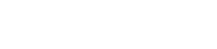- 「体重が落ちない」
「昔と同じ生活なのに太る」
そんなお悩みをお持ちの方へ - 肥満が引き起こす病気のリスク
- 体重が増え続ける原因
- 40代・50代から太りやすくなる?
- 体重増加・肥満の検査方法
- 体重増加・肥満に対する治療方法
- 無理なダイエットではなく「医療の力」で
体質から見直しを
「体重が落ちない」
「昔と同じ生活なのに太る」
そんなお悩みをお持ちの方へ
 肥満は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病の重大なリスク因子です。また、多くのがんのリスクを高めることでも知られています。健康のために痩せたいけれどうまくいかない・どうすればいいのか分からないという方は少なくありません。
肥満は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病の重大なリスク因子です。また、多くのがんのリスクを高めることでも知られています。健康のために痩せたいけれどうまくいかない・どうすればいいのか分からないという方は少なくありません。
体重増加や肥満に関連し、以下のようなお悩みがある方は、ぜひ一度当院にご相談ください
- 糖尿病、脂質異常症、高血圧症、脂質異常症など生活習慣病の診断を受けた
- 太り気味で、生活習慣病が心配
- BMIが25以上あり、生活習慣病を改善したい
- 腹囲がメタボリックシンドロームの基準を超えている(男性85センチ・女性90センチ)
- お腹だけぽっこりと出ており、内臓脂肪が心配
- 食事や運動に気をつけているつもりだが、なかなか体重が減らない
- 膝や股関節の痛みで、運動がしたくてもできない
- 生活習慣病の治療として減量を試みたが、うまくいかなかった
- 一時的に痩せることはできるが、毎度リバウンドをする
- 医師の指導のもと、科学的根拠のある減量に取り組みたい
肥満が引き起こす病気のリスク
肥満を原因とする病気、発症リスクを高めると言われている病気には、以下のようなものがあります。
これらの病気を予防するためにも、肥満の解消は重要なポイントになります。
- 2型糖尿病
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 高尿酸血症
- 脂肪肝
- 狭心症、心筋梗塞
- 脳梗塞
- 大腸がん、食道がん、肝臓がん、膵臓がん
- 乳がん、子宮がん、前立腺がん
- 睡眠時無呼吸症候群
- 変形性膝関節症
体重が増え続ける原因
 体重が増加する原因としては、食べ過ぎ、運動不足がよく知られています。ただ、ストレス・睡眠不足・加齢によっても、私たちの身体は「太りやすく」なります。
体重が増加する原因としては、食べ過ぎ、運動不足がよく知られています。ただ、ストレス・睡眠不足・加齢によっても、私たちの身体は「太りやすく」なります。
ここでは、食べ過ぎや運動不足以外の原因について、解説していきます。
自律神経の乱れや代謝の低下による脂肪の蓄積
ストレス・睡眠不足などにより自律神経のバランスが乱れると、代謝が低下します。これにより、脂肪が溜まりやすくなり、太ってしまいます。
体重増加に関係する細胞のバランスの変化
脂肪細胞には、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類があります。うち、脂肪をつくるのが、白色脂肪細胞です。一方の褐色脂肪細胞は、逆に脂肪を消費します。40歳くらいからは褐色脂肪細胞が減少し、白色脂肪細胞が増えるため、加齢とともに太りやすくなります。
食欲を左右するホルモンのバランスの乱れ
食後に分泌され満腹感をもたらす「レプチン」、空腹時に分泌され食欲をもたらす「グレリン」というホルモンがあります。正常に働いていれば問題はありませんが、睡眠不足などによってこれらのホルモンのバランスが乱れると、食べたのに満腹感が少ないといったことが起こり、過食、そして肥満の原因となります。
40代・50代から
太りやすくなる?
 年齢を重ねるにつれて「以前と同じ食事・運動量なのに体重が落ちにくくなった」「お腹まわりが気になるようになった」といった変化を感じる方が増えてきます。 その背景には、基礎代謝の低下や筋肉量の減少、ホルモンバランスの変化など、複数の要因が関係しています。
年齢を重ねるにつれて「以前と同じ食事・運動量なのに体重が落ちにくくなった」「お腹まわりが気になるようになった」といった変化を感じる方が増えてきます。 その背景には、基礎代謝の低下や筋肉量の減少、ホルモンバランスの変化など、複数の要因が関係しています。
中でも大きな影響を与えるのが、「ホルモンの変化」です。
女性の場合、30代後半から女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が少しずつ減少し、40代・50代にはその影響が顕著になります。エストロゲンには脂肪の蓄積を抑える働きがありますが、減少すると内臓脂肪が増えやすくなり、体重増加や体型の変化につながります。
男性も同様に、40代以降になると男性ホルモン(テストステロン)の分泌が徐々に減少していきます。テストステロンは筋肉の維持や脂肪燃焼に関わるホルモンであり、その低下により筋肉量の減少や内臓脂肪の増加、代謝の低下が起こりやすくなります。
さらに年齢とともに活動量の低下、睡眠の質の変化、ストレスの蓄積なども加わり、複数の要素が絡み合って「太りやすい体質」へと移行していきます。見た目の変化だけでなく生活習慣病や慢性炎症など健康へのリスクも高めるため、年齢に応じた体質の見直しや医療的なサポートが大切です。
体重増加・肥満の検査方法
体重が増えてしまう原因は、単なる食べ過ぎや運動不足だけでなく、ホルモンバランスの乱れ、慢性的なストレス、睡眠の質の低下、腸内環境の悪化、栄養不足など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多くあります。
特に、年齢とともに基礎代謝やホルモン分泌が変化する30代後半以降は、「努力しているのに痩せにくい」「急に太りやすくなった」と感じる方も少なくありません。そのため、見た目の変化や体重などの数値だけで判断するのではなく、体の内側で何が起きているのかを正確に把握することも大切です。
当院では、体重増加や肥満の「根本原因」を見極めるために適切な検査を行い、一人ひとりに合った治療法をご提案いたします。
血液検査(栄養解析)
一般的な血液検査項目に加え、体内の隠れた炎症や副腎疲労の程度、各種酵素の活性度、ビタミン・ミネラルバランスといった、分子栄養学的な項目を含めて調べます。栄養素の過剰・不足、血糖バランスやインスリン抵抗性の状態なども分かります。
唾液コルチゾール検査
唾液を1日に6回採取し、コルチゾールというストレスホルモンの分泌リズムを測定・分析します。副腎の疲弊度を知る上で不可欠なDEHAというホルモンも同時測定します。慢性的ストレス対する身体の反応、副腎疲労の有無・程度、日内リズムの乱れの有無などが分かります。
有機酸検査
尿中に排泄される100種類以上の代謝産物(有機酸)を調べる検査です。腸内環境や栄養素の代謝効率、ミトコンドリア機能、神経伝達物質の代謝、解毒機能などを多角的に測定し、身体全体の代謝経路の働きを把握します。この結果を活かし、栄養アプローチ、生活習慣指導を行います。
GI-MAP®検査
DNA解析を応用した、最先端の便検査です。腸の善玉菌・悪玉菌のバランス、ピロリ菌・カンジダ菌・寄生虫・カビの有無、腸の炎症状態、消化酵素の分泌状況、免疫機能などが分かります。自己免疫疾患や慢性疾患のリスク把握にも役立ちます。
毛髪ミネラル検査
毛髪に含まれる必須・有害ミネラルを測定します。体内の有害金属の蓄積と排泄の状況、身体のデトックス機能を把握できます。約40種類のミネラルの測定により、体内の必須ミネラルの過不足、ストレス・生活習慣の影響などが分かります。
エピクロックテスト
血液中のDNAのメチル化パターンを分析し、生物学的年齢を評価する検査です。加齢に伴う遺伝子発現の変化・修復力の衰えなどを把握することで、お一人おひとりに合ったエイジングケアが可能になります。
体重増加・肥満に対する
治療方法
NAD⁺注射
体内でのエネルギー産生に不可欠な補酵素(NAD⁺)を注射投与します。新陳代謝を活性化させる作用により、肥満の改善が期待できます。また、睡眠の質の向上、慢性疲労の改善、集中力・記憶力アップといった効果も期待できます。
プラセンタ注射
ヒトの胎盤由来のプラセンタ製剤には、成長因子・アミノ酸・ビタミンなどが豊富に含まれます。新陳代謝の活性化・血行促進などの作用により、肥満の改善が期待できます。また、自律神経のバランスの正常化、免疫力アップ、疲労・体力回復などの効果も期待できます。
各種点滴(肝臓デトックス、バイオリジェンスペシャル点滴、マイヤーズカクテル点滴など)
解毒作用促進・疲労回復促進などが期待できる肝臓デトックス点滴、総合的な健康サポートに役立つバイオリジェンスペシャル点滴、自律神経の調整・免疫力アップが期待できるマイヤーズカクテル点滴などをご用意しております。お身体の状態・症状に合わせて、メニューをご提案します。
ナチュラルホルモン補充療法
体内のホルモンと同一の分子構造を持つナチュラルホルモンを補充する治療です。血液検査・唾液検査の結果をもとに、患者様に合ったホルモンの補充を行います。肥満改善においては、新陳代謝の活性化などの効果が期待できるナチュラルホルモンをご用意しております。
無理なダイエットではなく
「医療の力」で
体質から見直しを
 世の中にはさまざまなダイエット法があふれていますが、一時的に体重が減っても、「すぐにリバウンドしてしまう」「体調を崩してしまった」という経験をお持ちの方も少なくありません。体重管理において本当に大切なのは、一人ひとりの体質や代謝の状態に合った方法で、内側から整えていくことです。
世の中にはさまざまなダイエット法があふれていますが、一時的に体重が減っても、「すぐにリバウンドしてしまう」「体調を崩してしまった」という経験をお持ちの方も少なくありません。体重管理において本当に大切なのは、一人ひとりの体質や代謝の状態に合った方法で、内側から整えていくことです。
当院では、無理な食事制限や急激な減量を推奨するのではなく、医療の視点から体質そのものを見直すアプローチを行っています。血液検査による栄養状態の分析、ホルモンバランスや腸内環境の評価などを通じて、体重増加の背景にある本当の原因を明らかにします。 そのうえで、再生医療(幹細胞治療や培養上清液)、ホルモン補充療法、点滴療法、栄養指導など、治療を組み合わせて、代謝を高め、脂肪がつきにくく、燃えやすい身体づくりをサポートいたします。
「痩せたいけれど、どうしたらいいかわからない」「努力しても変わらない」と感じている方こそ、ぜひ一度ご相談ください。医学的根拠に基づいた、安全で持続可能な体質改善をご提案いたします。